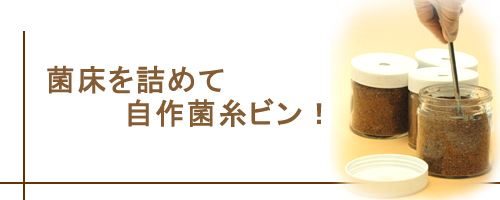 |
||||
|
||||
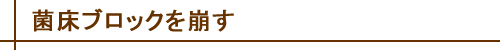 |
||||
 |
各メーカーから販売されている菌床ブロックの多くはそのまま菌糸ビンに入れることはできません。下準備として、袋から出して皮を剥く必要があります。 菌糸は雑菌やカビに弱いので、菌床ブロックに触れる道具や手は必ず洗ってから使用してください。消毒用のエタノールやゴム手袋を使えばさらに良いでしょう。 温度、湿度の高い夏はより注意する必要があります。 →菌床ブロック各種 |
|||
 |
皮を剥いた菌床ブロックをビンに詰められるように細かく崩します。 木片で手を怪我する場合があるので棒などで塊がないように崩していきます。ふるい等にこすり付けるようにすればさらに簡単に崩せますが、いずれの場合も雑菌の混入に気をつける必要があります。 すでに菌床ブロックを崩した便利な商品もあるので、そちらを使えば雑菌の混入も少なく、作業時間もグッと短くなります。 →崩し済み菌床ブロック →便利な用品 |
|||
 |
||||
 |
市販されている空きビン、プラスチックボトルに崩した菌床を詰めます。 菌床も生物なので酸素が必要です。ビンのふたに必ず穴を空け、フィルターをつける必要があります。 菌床を容器に詰める際はハンドプレス等を用いると容易に作業ができます。硬く詰めすぎると菌床全体に酸素が行き渡らなくなってしまうので詰めすぎに注意してください。 目安としては、容器の容量×1.2程度の菌床を詰めるとよいでしょう。 →空きビン各種 |
|||
 |
菌糸ビンを自作するメリットは容器を飼育種のサイズに合わせて作ることができることです。 プリンカップに詰めれば初令幼虫や超小型種用に使うことができます。 また、2リットル以上の大きなビンに菌床を詰めることで、蛹になる際にかなりの容量を必要とする超大型種に使用できます。しかし大型のビンは雑菌や温度管理などの点で難しいので、ある程度慣れてからの方が良いでしょう。 |
|||
 |
||||
 |
自分で詰めた菌糸ビン。詰められた菌糸は再生しようと活発になるため、ビン内の酸素の消費が大きく、菌糸ビン自体の温度も上がります。 この状態では幼虫を入れることができません。 菌糸が成長し、ビン全体が菌糸で覆われて白くなるまで寝かせ、1週間~10日ほど待ちます。 |
|||
 |
菌床を詰めてから約1週間。菌糸がビン全体を覆い白くなったら幼虫の投入です。既製品の菌糸ビンと同様に、幼虫が潜りやすいように穴を開けて幼虫を投入します。 菌糸がまだ活発に再生していて菌糸ビン内の温度が高く、酸素の消費量が大きいと幼虫が潜っていかないことがあります。 この場合は菌糸ビンのフタを開けておき、菌糸の活動が落ち着くまでさらに2、3日ほど待ってから幼虫を投入してみてください。 |
|||